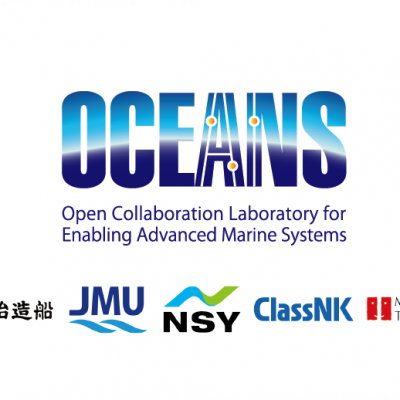目次
先進海事システムデザイン共同研究講座 一ノ瀬康雄特任准教授(常勤)

先生のご専門について教えてください
私の専門は船舶工学であり、特に船舶の流体力学と船型設計に関する研究を行っています。具体的には、計算流体力学(CFD)や機械学習、システムズエンジニアリングといった先端技術を駆使し、船舶の推進性能や実海域性能の向上、船型最適化に貢献することを目指しています。7~8年前から機械学習を用いた船舶設計プロセスを革新する研究を軸に研究をしており、現在の大阪大学工学研究科の先進海事システムデザイン共同研究講座(阪大OCEANS)では特に、生成AIによる海事産業の業務プロセスの改善を中心に研究しています。
どのような研究をされていますか?
現在は、生成AIを活用した船舶設計プロセスの革新に取り組んでいます。具体的には、大規模言語モデル(LLM)によるCAD設計支援システムの開発や設計知識データベースの構築、人とAIの協働による設計業務の自動化/自律化などの研究を通じて設計工数の大幅な削減を目指しています。
この道に進むことになったきっかけを教えてください
大学院の研究で流体の数値シミュレーションに興味を持ったことがキッカケで、国の研究機関である海上技術安全研究所に2009年に入所しました。そこで造船の仕事の大きさや、船舶工学研究の幅の広さと奥深さを実感し、船の世界の可能性に深くのめり込みました。研究を進める中で数値シミュレーションを機械学習で置き換える代理モデルの研究が、私の研究の軸となりました。その後、ノルウェー科学技術大学で在外研究中にChatGPTが発表されたと同時に、ChatGPTと当時開発した機械学習代理モデルを組み合わせた設計支援システムのプロトタイプ開発したのを契機に、生成AIの船舶設計への応用に興味を持ちました。そして2025年4月からは阪大OCEANSの特任准教授として船舶設計の生成AIへの応用研究に携わる機会を頂き、日本の海事産業の国際競争力向上に貢献することを目指して研究開発に取り組んでいます。
共同研究講座・協働研究所の利点
共同研究講座の大きな利点は、企業や関連機関と大学が緊密に連携し、共通の技術課題に深く取り組める点です。特に阪大OCEANSでは、世界有数の造船所や船級、船主といった海事クラスターの主要プレイヤーが一堂に会し、革新的なシステムズエンジニアリングと自動設計に関する基盤研究を推進しています。これにより、会社の枠を超えたビジネスプロセスの変革や、現場の知見を学術的に体系化する取り組みが可能となり、研究の質とスピードを大きく高められると実感しています。
企業が大学内で研究することの意義
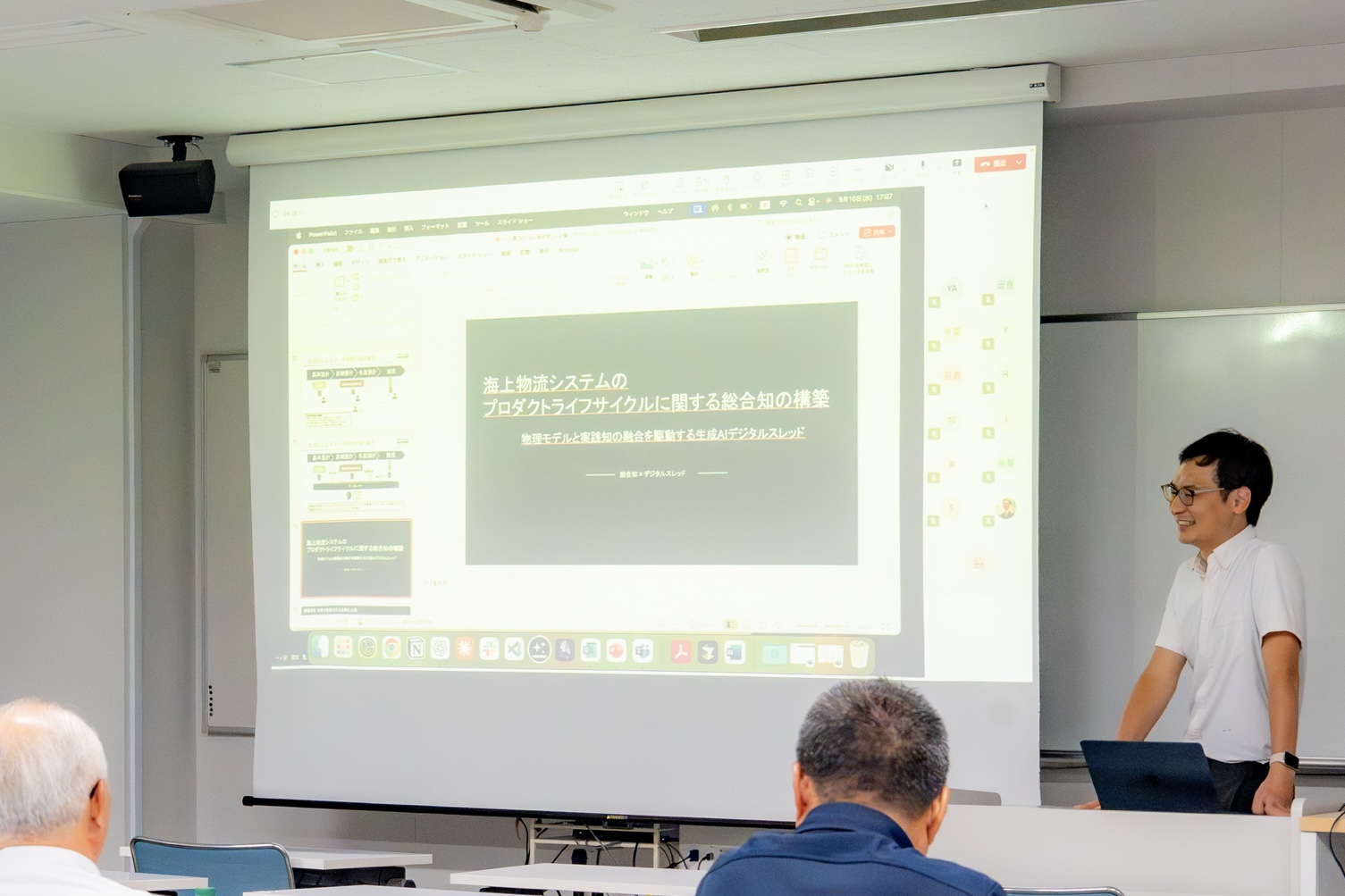
企業が大学内で研究を行う意義は多岐にわたります。まず、学際的で分野横断的なアカデミアの環境に身を置くことで、新たな刺激や気づきが得られます。また、大学がハブとなり、幅広い研究者や学生、そして他企業との交流が促進され、オープンイノベーションが加速します。これにより、企業単独では難しい根本的な技術課題の解決や、革新的な研究テーマへの挑戦が可能となり、結果として日本の製造業が積み重ねてきたノウハウをAIで知能化するなど、より普遍的で強い技術の創出に繋がると考えています。
この研究で難しいことは?また、研究が進まない時にはどうやって乗り越えますか?
船の価格は一隻、数億から数百億円規模にもなるため、生成AIが事実と異なる情報を生成してしまうハルシネーションの問題など、ミスの許されない設計においてAIを実際の設計現場に適用するにはさまざまな困難が伴います。特に、どの設計プロセスで、どのようなデータベースを活用し、いかに人とAIの協働を実現すべきか、は大きな問いです。一方で、造船業界は1970年代から他産業に先駆けてコンピュータ支援設計ツールを導入してきた長い歴史があります。生成AI時代においても、「設計と建造の目的やプロセスが変わらなければ、設計システムのアーキテクチャは普遍」という方針のもと、温故知新。これまでのノウハウや理論解析ツールを競争力の源泉とし、産業固有の知見をAIで知能化することで、最適なAI活用法を探求しています。
人々に伝えたいこと、メッセージ
今後、共同研究講座でやっていきたいこと、実現したい未来、 これから研究者、理系を目指す方々へ
阪大OCEANSでは、世界に冠たる日本の海事産業の国際競争力を高めるため、知識ベースを整理し、生成AIを活用することで設計工数の大幅削減とリードタイムの短縮を実現する未来を目指しています。また、現場の即応的なノウハウを学問として体系化し、普遍的な技術として社会実装に貢献したいと考えています。日本の造船業が高付加価値技術で雇用を創出し、技術開発で生き残っていける存在になることを願っています。 未来の研究者を目指す皆さんには、ぜひ自分の「好き」という気持ちを大切に、身の回りの現象に「ワクワク」しながら興味を持って探求し続けてほしいと願っています。